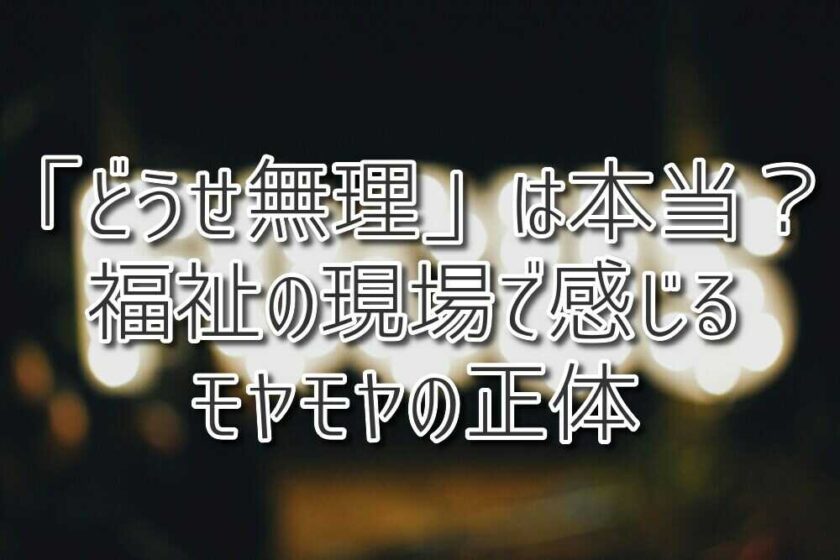我々のように、障がいのある子どもさんの支援をしていたり、それが大人の方への支援だったり。
はたまた上司と部下の関係で悩んでいたり、福祉の法律に関わるようなお仕事をしていると、「~だからできない」って感じることはありませんか?
これは、福祉の現場にいる人なら、よくある感覚だと思うんですよね。
たとえば…
「重度知的障害の子どもだから、自立の支援はできない」
「立地の悪いところに施設があるから、支援者が集まらない」
「支援者に専門的な知識がないから、虐待や身体拘束が横行してる」
「上司が福祉のことを理解してないから、話が通じない」
…こういう話、あると思います。
「だから無理」
「だからできない」
「どうしようもない」
「やってもしょうがない」
そんなふうに思ってしまう気持ち、すごくよくわかります。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみてほしいんです。
たしかに、みんながそう言ってると、「それが正しいのかな?」って思ってしまうかもしれません。
でも、本当にそうなんでしょうか?
福祉の仕事って、もうどうにもならない状況ばかりで、改善なんてできないまま、つらいことばっかりなんでしょうか?
「~だから」という理由を前にしたとき、「夢を語っても無理だよ」と感じるかもしれません。
でも、それって、「~の部分が変えられる」って、どこかで思っているからじゃないでしょうかね?
変えられると思ってるけど、実際は変えられない。
じゃあ、無理やん…ってなる。
この考え方、多くの人がつい使っちゃいがちなんです。
ここがポイントで…
そもそも、「~」の部分って、本当に変えられないことなんでしょうか?
本当は、「変わってほしい」と思ってるんじゃないですか?
でも、残念ながら、そこは変わらないことなんです。
変わらないものを、どうにかしようと悩んでしまう。だから、苦しくなっちゃうんですよね。
そんな思いを持っている支援者や親御さんはきっと、「~」を「課題」だと思ってるんだと思います。
課題っていうのは、「改善できるもの」って意味ですよね。
でも実はそれ、「課題」じゃなくて「条件」かもしれません。
この「課題」と「条件」の違いって、すごい大事なんですよ。
「条件」っていうのは、もう変えられないもので、受け入れるしかない土台みたいなものです。
その上で、どうするかを考えることが大切なんですよね。
変わらない「条件」の上で、自分が何をできるか?これを考えられると、行動も支援方法も変わってきます。
逆に、「これは課題だ」と思い込んでると、そこに気持ちが取られすぎてしまうんです。
さっきの課題を条件に変えて考えてみると…
「お子さんが重度という前提で、どんな自立の形があるだろう?」
「立地の悪い場所にある施設だけど、どうしたら支援者が集まるだろう?」
「専門性のある支援者がいなくても、虐待とか身体拘束を防ぐためには何ができるだろう?」
「福祉のことを知らない上司と一緒に、どうすればより良い支援ができるだろう?」
…こうして考えると、なんとなく視点が変わってきませんか?
これまで、「無理だよね」「難しいよね」と思っていたことの多くは、実は「課題」ではなく「条件」だった、なんてことも多いはず。
もし、「無理だ」「難しい」と感じることがあったら、こう考えてみてください。
「これは課題?それとも条件?」
「もし条件なら、その前提で自分にできることは何だろう?」
この考え方ができるようになると、気持ちもグッと前向きになるはずです。
変えられないことを前にして、ただ落ち込んでしまうのはもう今日でおしまいです。
条件は条件として受け入れて、その上で自分にできることを見つけていきましょう。
そうすれば、これからの支援の在り方が、少しずつでも変わっていくはずですよ◎
お問い合わせはこちら